中島直人さまの
『都市計画の思想と場所
日本近現代都市計画史ノート』
を読みました。
著者の中島直人さんは、東京大学大学院で都市計画論、都市計画史、都市デザインを研究している先生です。
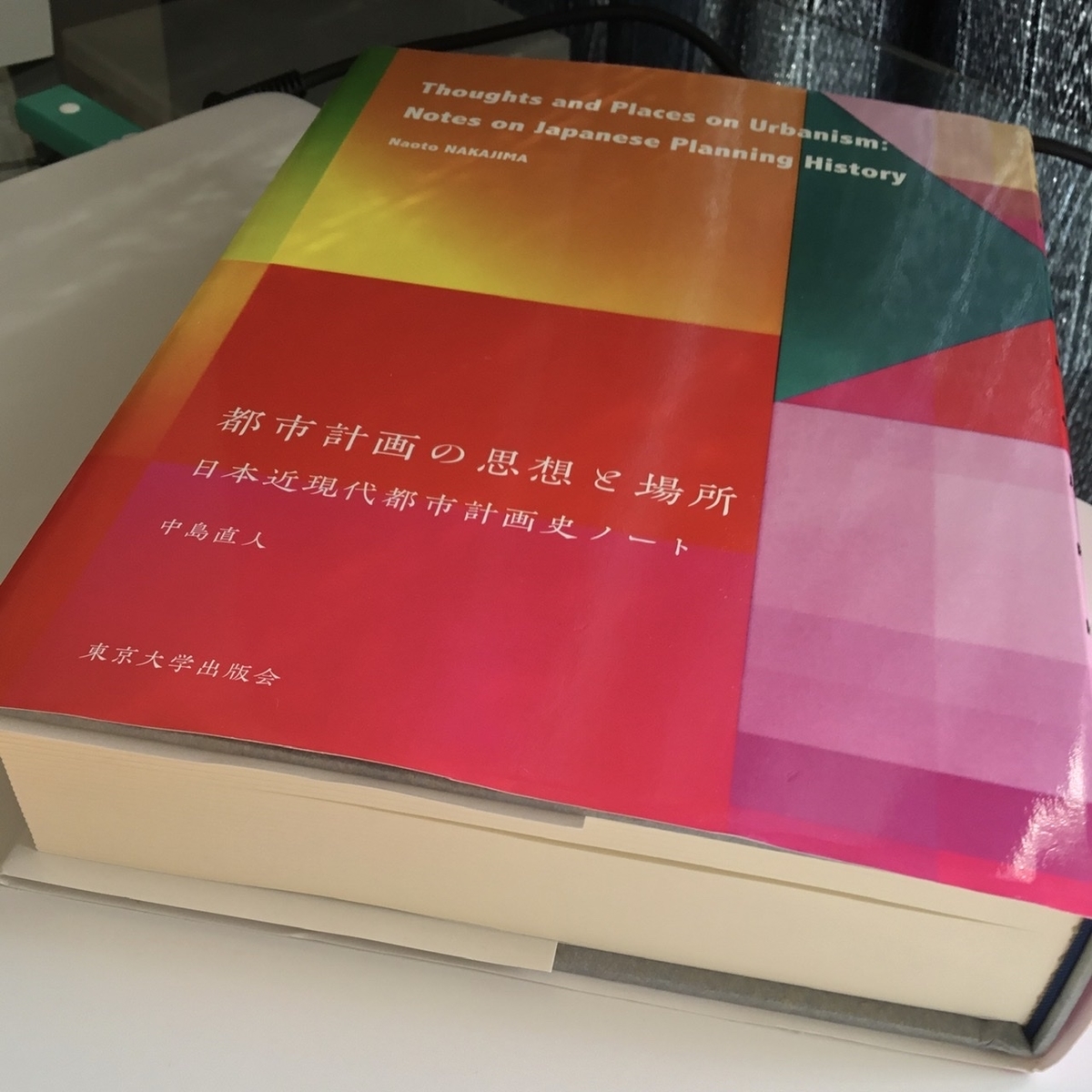
都市計画の策定や市街地再開発事業などの街づくりの仕事をしている人がいます。
また、不動産デベロッパーで同様の仕事をしている人もいます。
多分、そう言った方を読者として設定しているのでしょう。
でも、計画の策定手法のような技術的な事を書いたものではありません。
街づくりに取り組んできた先人についての記述が多くありました。
そういうことで、街づくりの仕事をしている人の精神的な教科書的なものでした。
よかったですよ、この本。
「よかった」って、雑な表現ですけど。(笑)
商業開発に興味・関心がある私にとっては。
私は計画的につくる商業施設の開発にその限界を感じていました。
私の思いを言葉を変えて、代弁していただいて感じです。
街づくりも商業施設の開発もある意味同じだと再認識した次第です。
この本の中で、心に響いたところを転載したいと思います。
*******************
都市美運動
=都市像の創造
①石川栄耀
市民の親和
=コミュニティ
思想 都市の本質 賑わいが生み出す市民同士の隣保的親和
目的 市民主体の生活空間の創造
→商業環境、盛り場
②豫内吉胤
都市の個性
前提 画一的な街づくりへの批判
→町並み、歴史的環境、河川・濠
③石原憲治
生理的な感覚
=アメニティ
→公共空間 →快適性と健康性を基盤とする都市空間づくり
①〜③の共通点
・ 生活の場としての都市
石川栄耀
人はなぜ都市を作るのか?人は、「集まってその集まりをたのしむ」「市民相互を味わう」「人なつかしさの衝動」のために都市を作るのだ。
あらゆる地域、あらゆる時代のとしは、中心部に美しい広場を持っていて、その都市美的環境のもとに市民が集まって歓談を楽しんできた。そうした中心のことを「盛り場」と呼んだ。今日都市からこの盛り場を無くしたら都市はない。都市がない所か「人間そのもの」がなくなるのである。
「「都市計画」は「計画者が都市に創意を加えるべきものではなくして」それは都市に内在する「自然」に従い、その「自然」が矛盾なく流れ得るよう、手を貸す仕事である」
三春町建築賞の講評
「"らしさ"というものは過去にすでに出来ていたパターンではなく、これからの三春をつくって行く、その行き方、考え方、その働き、流れの中に、ある特色、傾向として形成されてくるものが、"三春らしさ"ではないだろうか。"らしさ"青い鳥ではなくて、それを追い求め、探し続ける私たちの軌跡が"らしい"を形成する。」
レイモンド・アンウィン
「都市美はコミュニティの表現に他ならない」
郊外に住まう一人ひとりは環境の消費者に終始するのではなく、「郊外生活文化」の担い手、その風景をつくり出す人々として期待された
「都市計画は(中略)「完成品」計画ではあり得ず、発展のプログラムでなければならない。(中略)常に豊かで総合的なすぐれた「構想計画」に先導されていなければならない。」
*******************
他にも感じる文や言葉はたくさんありました。
全部書くと大きな量になってしまいますので、これくらいにしておきます。
商業施設の開発に取り組んでいて、これでいいのかという不安を常に持っていました。
また、導線計画などと言って、お客様にどう建物の中を動いてもらうかなどを計画していました。
それって、作っている私の驕りではないかと。
都市計画も商業施設も利用者の感覚や思いが一番なんです。
そして、商業施設も不動産です。
その土地の歴史や住民や訪問者や働いている人の経験や記憶があります。
それが重層的に作られた何かがあるのです。
商業施設の開発を行う人もマンション開発を行う人もそういうことを考えてつくらなければいけないのです。
どこの場所にも同じ建物を作ってはいけません。
今回も訪問記では無かったです。
ステイホーム実践中の私の日記だと思って許してください。
最後まで読んでいただいた奇特な方、ありがとうございました。
コロナ禍の中、熱中症にも気をつけてお過ごしください。
2020年8月6日(木)